私たちは、2024年に築27年戸建てを購入した30代夫婦です。
私たちの世代は、これから先の人生長い世代です。転職・転勤もあるかもしれないし、結婚するかしないか、子供ができるか、まだ不確定なことも多いと思います。
なかには、家を買う?買うならいつ?どこに?と悩んでいる方もいるかもしれません。
家を買うタイミングについては、以前こちら↓の記事で紹介しました。
家を買うことが決まったら、次は家を買う場所の問題。
というのも、賃貸と違って、家を買ってしまうと気軽に引越しができません。
そのため、家を買う場所はとても重要です。
家の場所選びは、個人の生活スタイルや何を重要と考えるかによって変わってくると思います。
そこで、今回の記事では私たち30代夫婦が家を買う場所を選ぶ時に考えたことを紹介します。
この記事を読むことで、自分はどのような基準で家の場所を決めるか?を考えるきっかけになればと思います。
☆この記事はこんな方におすすめです☆
30代夫婦(+子2人)、家をどこに買うか問題

まずは、私たちのプロフィールを簡単にご紹介します。
・家族構成…30代半ばの夫婦と、子供2人(6才、2才)
・夫婦共働き
・関西某所在住
・結婚9年目、これまでは賃貸のマンション暮らし
子供の預け先を考える
保育園や幼稚園
夫婦共働きの場合、仕事をするには、子供を保育園に預ける必要があります。また、3才(年少)から幼稚園に通いはじめるご家庭もあると思います。
そこで、家の場所を決めるにあたっては保育園/幼稚園との距離が重要です。
なにしろ、毎日の送り迎えはなかなかハードです。
もしまだ子供が保育園/幼稚園に通っていないなら、家の近くの園、そして園の定員についても調べておくのがよいと思います。
自転車や車が使える場合は、すこし遠くの園も候補に入れることができます。(ただし、イヤイヤ期に自転車に乗ってくれない場合があったり、雨の日に自転車に乗る覚悟も必要です…。)
もしすでに保育園に通っている場合、遠い距離での引越しは保育園探し(いわゆる保活)も同時にする必要があり、難易度がかなり上がります。
私たちの場合
保育所の空き状況を自治体HPで調べましたが、2人とも転園できそうな保育園はありませんでした…。場合によっては電車通園かな…と覚悟し、数駅先までは家探しの候補としていました。結局、近くで家が見つかり事なきを得ましたが、家探しと保活の両立の難しさを感じました。
小学校
子供が小学校に入学してからであれば、家の場所を考えるのはすこし楽になると思います。
なぜなら、ほとんどの地域では住む場所によって校区が決められているためです。
そのため、保育園の場合とは違い、空き状況を気にする必要がありません。
そのかわり、他の小学校の校区に引っ越す場合には転校することになります。
例外として、近くの小学校校区に引っ越す場合には学校と市町村の役所で指定校の変更手続きをすることで、今までの小学校に通い続けることができる場合があります。
また、両親が共働きの場合は学童保育の預け先について調べておく必要があります。
実家との距離
実家との距離も、家を買うエリアを決めるうえで重視したポイントです。特に子供が小さいうちは、実家が近くにあると、いざという時に頼れるのでありがたいです。
個人的な考えになりますが、実家からマイホームへの所要時間と、行き来するときの心理的・体力的な負担は、だいたい以下のような感じかな〜と思います。
実家からの所要時間の目安
30分程度 ・・・ 週に何回か行き来することができる
1時間程度 ・・・ 日常的に通うのは大変だが、たまに来てもらうことはできる
1時間半以上 ・・・ 頑張れば、数ヶ月に1回来てもらうことができそう
私たちの場合
夫の勤務地の都合もあり、妻の実家に1時間、夫の実家に3時間程度で行けるエリアで家を探すことに決めました。
駅との距離、周辺の環境
駅からの距離
もうひとつ、家の場所を考えるにあたって重要な条件があります。それは、駅からの距離です。
私たちは、家の場所は、駅徒歩15分以内に絞って探しました。
駅近のメリットは、何といっても、通勤、通学に便利ということです。
私たちの場合
近年ではリモートワークが可能な仕事も増えてきましたが、私は週5日の電車通勤をしています。よって、家から駅までの距離が近いほど通勤には便利です。
また、恥ずかしながら、私は運転免許を取って以来15年・数回しか運転経験がないという、筋金入りのペーパーゴールドです。
さらには、私は幼少期、最寄駅まで自転車で20分の陸の孤島に住んでいました。駅が遠いと、通学が大変なんです。雨の日もカッパを着て自転車に乗ること20分、なかなかの辛さです…。
そんな経験をしてきたものですから、家は、絶対駅の近くがいい!!
と夫に頼み込みました。
ただ、駅から遠い物件にもメリットがあります。
それは、理想の広さや条件の家が安くで手に入る可能性が高いということです。
物件サイトを見てみても、鉄道の駅から遠いエリアでは駅近の物件よりもかなり安かったり、庭付き、日当たり良好、敷地面積が広い物件が見つかりやすい印象です。
例えば、在宅ワーク中心で電車に乗る必要がなかったり、車やバスに乗る生活を中心に考えるのであれば、駅から遠い場所を候補に入れるのもありだと思います。
周辺の環境
家を買う場所を選ぶにあたっては、周辺の環境も重要だと思います。
特に子育て世代は、次のような施設が近くにあるかをチェックしておくのがおすすめです。
反対に、子供の安全を守るため、次のような場所の存在も確認しておきましょう。
特に、行ったことがない地域で家探しをするときは、物件の内覧のときでもよいので、一度は自分の足でその地域を歩いてみるのがよいと思います。
自治体の制度や助成金をチェックしよう
子育ての支援制度は、どこの都市も同じというわけではありません。そのため、住む場所を決めるにあたっては、その市町村の子育て支援制度についても調べておくとよいでしょう。
以下に、その一例を紹介します。
こども医療費の負担
例えば、子供が病院にかかった時に使う、医療費助成制度。対象となる年齢や助成額も、市町村によって様々です。私が住んでいる関西の代表的な都市(大阪市、京都市、神戸市)の制度を比較してみました。
| 大阪市 | 自己負担額(1医療機関ごと) 0歳から18歳まで 1日当たり 最大500円(月2日まで) ※同一医療機関における3日目以降は自己負担なし 参考:大阪市HP/こどもの医療費を助成します |
| 京都市 | 自己負担額(1医療機関ごと) 0歳から小学6年生まで:入院・通院ともに200円/月 中学生:入院 200円/月、通院 1500円/月(複数の医療機関を受診して月の合計が1500円を超えた場合は申請により超えた分の支給を受けることができる) 参考:京都市HP/【福祉医療】子ども医療費支給制度 |
| 神戸市 | 自己負担額(1医療機関ごと) 0歳から2歳まで:通院、入院ともに自己負担なし(0円) 3歳から高校生まで:通院は1日最大400円を月2回までの負担(3回目以降、自己負担なし)、入院は自己負担なし(0円) 参考:神戸市HP/こども医療費助成 |
※2024年12月現在。詳細は、各自治体のHPをご確認ください。
その他の子育て関連制度
その他の子育てに関する制度も、市町村によって様々です。
たとえば東京都では、都内在住の0歳から18歳までの子供を対象に月額5000円を支給する『018サポート』という制度があります。参考:(東京都HP 018サポート)
他にも、産前産後の支援や保育園の申し込み方法も市町村によって変わります。
なかには、高校の授業料の補助・無償化の制度がある市町村もあります。
高校ともなるとまだまだ先の話ですし、子供が高校に入学する頃には制度の内容が変更になっているかもしれません。
しかし、先のことを見越して、引越し先にどのような制度があるのかを調べておいて損はないと思います。
暮らしていく街を選ぶために、大事なこと
《自分たちの生活》にあった場所を選ぶ
家の場所を選ぶうえでは、自分たちの生活に適した場所を考える、というのが重要です。
主な移動手段として車を使うか、電車を使うか、といった生活スタイルによって、最適な家の場所は変わってくると思います。
また、子供が小さいうちは預け先の問題があり、家探しができる範囲が狭まってしまうかもしれません。そのため、早いうちから家の情報や子供の預け先のリサーチをすることをおすすめします。
前の章で紹介したとおり、市町村によって子育ての制度は様々です。また、なかには若年世代の住み替えに補助を出している自治体もあります。
公的な制度もうまく活用しながら、住む場所を考えてみてくださいね。
歩いてみることの重要性
様々な条件を考えたうえで家を買う場所を決めるとき、最終的な決め手になるのはこの街で暮らしたいという気持ちなのではないかと思います。
たとえば、おしゃれなカフェがあったり、お散歩ができそうな広い公園があったり、子育て世代が多く、活気がある雰囲気だったり。
そういった街の魅力を感じるには、実際に地域を歩いてみるのが一番です。
私たちの場合
私たちも、家探しの前に、候補地をいくつか歩いてみました。
広い公園があり、歩いていると近所の方が声をかけてくれる素敵なところもありました。
なかには、駅前が寂れた雰囲気だったり、坂が急だったりと、そこに住むイメージが浮かばない場所もありました。
結局家を購入した場所は、それまで住んでいたところから徒歩25分(距離にして約1.5キロ)の距離でした。近くでしたが、何回か下見に行きました。
周辺の家、道路や近くにある公園の雰囲気、小学校の通学路の様子など、地図では分からないことを体験することができ、住んでからの生活がイメージしやすくなりました。
お気に入りの街を見つけて、納得のいく家探しができますように。


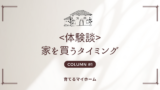



コメント